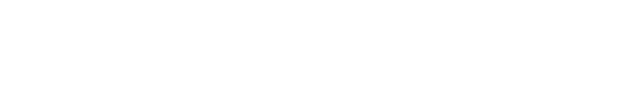5.当院の胃カメラの工夫
◆胃カメラを楽に受けて頂くための4つの工夫◆
◆質の高い検査(小さな病気の発見・見逃しをしない)ための4つの工夫◆
■楽に受けていただくために■
①鎮静剤(静脈麻酔)
胃カメラ検査の際のオエっとなる反射を抑えるため、点滴から薬を入れて眠った状態(無痛胃カメラ)で検査を受けて頂けます。
鎮静剤にも「眠る作用が強いもの」「反射をとる作用が強いもの」などいくつか種類があり、問診や過去の検査の履歴・患者さんご自身の咽の反射の強さなどの体質を伺い、適切な種類・量を選択します。
また、『楽に受けたいけど検査の画面は見たい』『完全に眠るのは怖い』と言った方には、スコープの細さを調整して、軽めの鎮静剤でボーっとしたような状態で受けて頂くことも可能です。
※鎮静剤の安全性について
鎮静剤(静脈麻酔)は量を多く使いすぎると、呼吸抑制などの副作用がありますが、当院では患者さんお一人お一人の性別・体重・年齢と反射の強さに合わせて、薬の量を0.1㎎単位(1gの1万分の1)で調整し検査を行っております。
さらに、アレルギーなどの副作用に対してもすぐに対応できるように、検査中は全身状態を把握するモニターをつけております。
これにより必要最小限の薬の量でも無痛で、かつ副作用の頻度も少なく安全に検査を行うことができます。
※以前に他院で鎮静剤を使って効かなかった方へ
鎮静剤が効かないのには理由があり、当院ではそのような方にも対応できるような体制で検査を行っております。詳細は「なぜ鎮静剤が効かないの?」をご参照ください。
→ → → → → → topへ
②カメラの細さの選択
鎮静剤をご希望されない方でも楽に受けて頂けるように、患者様の反射や緊張の強さに合わせてカメラの細さを調整して検査を行います。
例えば咽の反射が強い方には、先ほどご説明した舌への刺激が少ない専用のマウスピースを使用して経鼻内視鏡用の細いスコープを口から挿入したりします。
※現在は経鼻内視鏡用の細いスコープについてもオリンパスの最新式のハイビジョン内視鏡(GIF-1200N)を用いており、従来の経口内視鏡スコープと変わらないクオリティの検査がお受け頂けます。(詳しくはこちら)
③炭酸送気
オエっという反射に加え、胃カメラの検査がつらいと言われる大きな理由に胃の張りがあります。
検査中は胃の中に空気を送り膨らませた状態で隅々まで見落としのない様に観察するため、どうしても空気による張りが起こってしまいます。
当院では、空気の100倍吸収が早くお腹の張りが少ないと言われる炭酸ガスを用いて検査を行っております。
これにより検査後のお腹の張りが劇的に少なくなり、検査後もスムーズにご帰宅頂けます。
④リカバリールーム
検査後に鎮静剤が体から抜けるまでのあいだ、ゆっくりお休み頂けるスペースを用意しております。
→ → → → → → topへ
■質の高い検査(小さな病気を見つける・見逃しをしない)ために■
①次世代内視鏡システム「EVIS-X1」
いくら小さな病気を見つけようとしても、画面に映らなければ見つけられません。
当院ではオリンパス製の最新の次世代内視鏡システム「EVIS-X1」を使用し、見つけるのが難しいといわれている数ミリの微小なガンの早期発見にも力を入れております。
※次世代内視鏡システム「EVIS-X1」の詳細はこちら
→ → → → → → topへ
②色素散布(インジゴ・ヨード)
検査中に気になる部位を見つけた際に、色のついた液体(インジゴカルミン)を散布することで病変の凹凸などをしっかり観察することが出来ます。
また、食道のガンが疑われた際にはNBI(後述)という方法や、ヨードという色素を撒いてがんかどうかを詳細に観察します。
→ → → → → → topへ
③酢酸
胃がんは酢酸を散布することで、色が変化するという性質があります。
検査中に怪しいと思う病変を見つけた場合、酢酸を散布し胃がんか否かを見極め、さらに色素を上からかけることでその広がりまで観察することが出来ます。
→ → → → → → topへ
④NBI
NBIという色調を変えて観察する方法があります。
この観察法により、これまでは早期発見が困難であった食道がん・咽頭がんなどの病変を見つけることが出来ます。
当院のNBI観察は従来のものをさらに向上させた第2世代のNBIを用いており、病気の発見率がさらに上がりました。
また、NBIを用い病変を詳細に観察することで、ガンか否かを見極めることが出来、無駄な生検検査を減らすことにも役立ちます。
→ → → → → → topへ
⇒Next:6.胃内視鏡(胃カメラ)の費用
⇐Back:4.胃内視鏡(胃カメラ)を受ける時の流れ・かかる時間
文責:神谷雄介院長(消化器内科・内視鏡専門医)
<目次>
3.胃内視鏡(胃カメラ)の方法 ~経鼻・経口・鎮静剤の選択について~
→楽に受けれる4つの工夫・見逃しをなくす4つの工夫
8.検査予約
→ → → → → →胃内視鏡(胃カメラ)Topへ
→ → → → → →ホーム