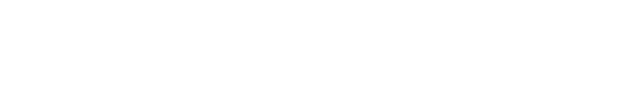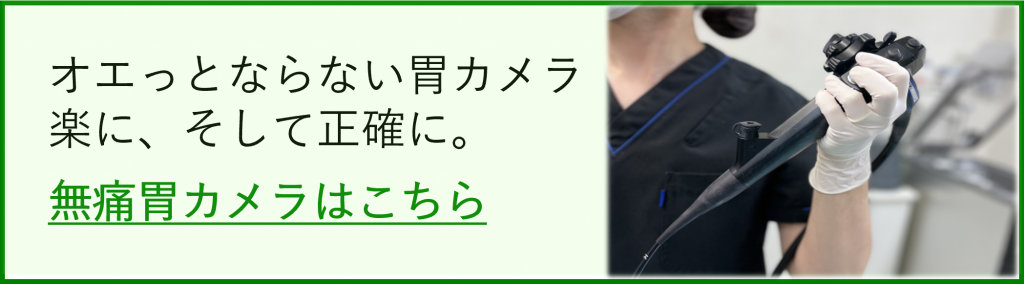カンピロバクター腸炎
カンピロバクター腸炎とは
カンピロバクター菌感染による腸炎で、主に食中毒として起こります。
カンピロバクター菌自体は鶏や牛など等の畜産動物をはじめ、ペット、野鳥、野生動物など多くの動物が保菌しています。
これらの動物が腸炎を発症することはありませんが、経口摂取により人の体に入ってくると腸炎を発症します。
感染経路
- 生や加熱があまりなされていない鶏肉(鶏刺し、鶏のタタキ、バーベキュー・鶏鍋・焼き鳥などでの加熱不十分な鶏料理)
- ホルモン料理
- 鶏肉など調理過程の不備で二次汚染された食品(鶏の生肉を切った包丁やまな板でそのまま調理された料理など)
などを摂取することで発症します。
食べてからすぐ発症することは少なく、一定の潜伏期間(2~5日、長い時は1週間程度)後に発症します。
症状
症状は腹痛・下痢・嘔吐などの腸炎症状が多く、悪寒・発熱や血便を来す場合もあります。
またカンピロバクター腸炎後発症後1-3週間後に、手足のの筋力低下・麻痺や顔面神経麻痺、呼吸困難などを起こす「ギラン・バレー症候群」と呼ばれる神経疾患をを発症する場合もあります。
検査
症状からだけでは
なども考えられるため、腹部エコーや血液検査・培養検査、場合によっては大腸カメラなどを行い診断を行います。
<腹部エコーの画像>
実際のカンピロバクター腸炎のエコー検査の画像です。水色矢印の範囲で大腸が浮腫んで粘膜下層が炎症で白く見えます (黄色矢印)
<大腸カメラの画像>
実際の大腸カメラの画像です。大腸と小腸のつなぎ目のバウヒン弁と呼ばれる部分に出血やびらんなどの炎症を認めました(緑矢印)
◆関連ページ:
治療
症状を和らげるような内服薬・食事指導、必要に応じて抗生剤の使用などを行います。
①内服治療;整腸剤 漢方薬
下痢・腹痛といった胃腸炎症状を和らげます。
②抗生剤
症状や炎症が強く悪化の懸念がある場合に使用します
③食事指導・点滴
下痢による脱水予防のためOS1やポカリスエットなどの体に吸収されやすいものをこまめに摂取すること
(経口摂取が難しい場合には点滴も行います)
炎症のため消化吸収機能が十分に働かないためおかゆなどの消化しやすいものを召し上がっていただくこと
などを行います。
※下痢止めについて;
下痢によって腸内の菌を排出しているため、下痢止めによって下痢を止めてしまうと菌が腸内に留まってしまい、結果改善が遅れてしまったり重症化することがあるため、基本的には下痢止めは使用しないことがほとんどです。
予防
カンピロバクターは過熱に弱いため、十分に加熱して食べることが予防につながります。
(中心部を75℃以上で1分間以上加熱することでカンピロバクター菌を殺菌することが可能です。)
焼き肉店・焼き鳥店やバーベキューなどでの発生率が高くなっています。
鶏刺し・鶏のタタキなどの生食のものは避け、焼き肉店やバーベキューなどでは十分加熱して「生焼け」を食べない様に心がけましょう。
(特に原因となりやすい「鶏肉」や「牛レバー」はしっかりと加熱しましょう)
また家庭では二次汚染防止のために、
・生肉は他の食品と調理器具や容器を分けて処理や保存を行う
・生肉を取り扱った後は十分に手を洗ってから他の食品を取り扱う
・生肉を使用した包丁やまな板でそのまま別の食品を調理しない(※使用後に洗浄や熱湯をかけて殺菌を行ってから使用するようにしましょう)
といったことも大切です。
症状でお困りの方はお力になれますのでご相談ください!
◆関連ページ:
文責:巣鴨駅前胃腸内科クリニック院長 神谷雄介
(消化器学会・内視鏡学会専門医)