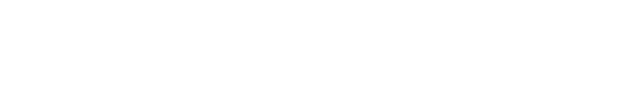食欲不振外来

「お腹がすかない」、「食欲がない」、「食べたいはずなのにいざ食べると大して食べれない」
このような症状を経験した方も多いと思います。
いわゆる「食欲不振」と呼ばれる症状ですが、その症状の裏には病気が潜んでいることもあり、原因をはっきりさせ、しっかりと治していきましょう
<目次>
1.そもそも食欲不振とは?
~意外と怖い“食欲不振”~
食欲不振とは、“食べ物を食べたい気持ちが起こらない状態”や“食べたいのにあまり量が食べられない状態”などをさします。
「気にはなる症状ではあるけど、特に日常生活に支障はない」ということでそのまま過ごされる方もおられるかもしれませんが、食欲不振は病気のサインのこともあり、そのままにしておいて病気が進行してしまった、などということにもなりかねません。
私たちが生命活動をするためには栄養を取ることは必要なことであり、そのための食事がとれなくなっているということは、思っている以上に“普通ではない状態”なのです。
特に下記のような症状を伴う方は病気による食欲不振の可能性があり、一度外来を受診することをお勧めします。
①長期間(2週間以上)続く食欲不振
②体重減少を伴う食欲不振
③食べ物を食べても味がしない
④60歳以上の方
⑤胃痛・腹痛・嘔吐・黄疸などの他の症状を伴っている食欲不振
→ → → → →食欲不振外来top
→ → → → → →ホーム
2.食欲不振の原因は?
食欲不振の原因は大きく分けて4つあります。
A.心因性:ストレスやうつ状態による食欲不振
B.機能性:胃や腸の働きの低下による食欲不振
C.器質性・症候性:癌や内分泌疾患など病気による食欲不振
D.薬剤性:薬の副作用によって起こる食欲不振
それぞれの 特徴を見ていきましょう。
A:心因性
心因性とは文字通り、「心」つまり精神的な部分が影響して起こる食欲不振です。
もともと“食欲”は脳の視床下部という部位がコントロールしているのですが、ストレスが続いたりやうつ状態になると視床下部の働きが乱れ“食欲”という信号自体が発生しなくなってしまい食事が食べたくないという状態になってしまいます。
さらにうつ状態が進行すると、食べても味がしない・砂のような感じがするといった味覚の低下まで起こってきてしまいます。
B:機能性
機能性食欲不振とは胃や腸の動きや消化・吸収力の低下などによって起こるものです。
最近では機能性ディスペプシアとも呼ばれています。
胃や腸などの消化器の機能は自律神経が調整していますが、疲れやストレスなどが続くと自律神経の働きが低下してしまい胃や腸がうまく動かくなってしまいます。
また夏場に夏バテや熱中症気味になり脱水傾向になると、消化器系にうまく血液が循環せず動きが低下することもあります。
そうすると「胃が動かないので食欲自体もわかない」、「食事をとってもすぐにお腹が張ってしまい量が食べれない」、という状況になってしまいます。
※関連ページ;機能性ディスペプシアについて
C:器質性・症候性(病気によるもの)
心因性や機能性は、ストレスや疲れ・暑さなどによる周囲の環境が影響しておこる食欲不振ですが、器質性・症候性は何らかの病気による食欲不振です。
代表的な疾患にはこのようなものがあります。
・がん(胃がん・膵臓がん・大腸がんなど)
・ピロリ菌胃炎(いわゆる慢性胃炎)
・甲状腺機能低下症
・電解質異常 など
①がん
がんがつくり出すサイトカインという物質によって代謝の異常や電解質の異常が起こり、エネルギー消費量が増加し、胃や腸など内臓機能を働かせるためのエネルギーが確保できなくなります。それより胃の機能低下が起こり食欲不振や体重減少などが生じます。
また、胃がんや膵臓がんなどの消化吸収に関わる臓器のがんは消化機能にも影響するため、食欲不振が起こりやすくなります。
特にがんの発生率が増加してくる60歳以上の方で体重減少を伴う食欲不振は要注意と言えます。
②ピロリ菌胃炎
ピロリ菌に感染すると萎縮性胃炎という慢性胃炎が起こります。長年経過することで胃の蠕動機能や消化機能が低下し食欲不振の一因にもなってきます。
③胃潰瘍・十二指腸潰瘍
胃潰瘍や十二指腸潰瘍ができると、胃に食べ物が残っている感覚がするため、満腹感によって、食欲不振が起こるとされています。痛みを伴うことが多く、放っておくと穿孔(胃や腸に穴があくこと)することもあるため、痛みを伴う食欲不振は早めに病院を受診することが大切です。
④甲状腺機能低下症
甲状腺は体の生命活動を維持するためのホルモンを分泌している臓器ですが、甲状腺機能低下症に陥るとホルモン分泌が低下し、体の活動性が下がってきて食欲が低下します。
甲状腺機能低下症の場合は、食欲が低下しものが食べられないのに体重が増加傾向にあるのが特徴です。
⑤電解質異常
血液中のナトリウムなどの電解質が異常をきたすと食欲不振を来すことがあります。腎機能異常や熱中症などで起こってきます。
D:薬剤性
薬剤性の食欲不振は、痛み止めの薬や抗生剤、向精神病薬や抗がん剤などの副作用で起こることがあります。
→ → → → →食欲不振外来top
3.検査は?
<問診>
食欲不振の発症時期・程度・体重減少などの付随症状や生活環境、飲んでいる薬の状況を伺います。
問診で原因の予想がつくことも多く、しっかりとお話を伺い患者さん自身の生活背景を知ることも大事になってきます。
<血液検査>
甲状腺などの代謝異常や電解質の状態を確認します。
<腹部レントゲン>
胃や腸管の動きに関連するガスの状態などをチェックします。
<エコー>
消化器系のがん(肝臓がん・膵臓がん・胆のうがん)などの病気の検索を行います。
また、大きな病変であれば胃がん・大腸がん、胃潰瘍や十二指腸潰瘍などの胃や腸の病変もエコーでわかることが多いです。
<胃内視鏡(胃カメラ)>
胃カメラで食道・胃・十二指腸を直接観察し、食道がん・胃がん、胃潰瘍・十二指腸潰瘍、ピロリ菌による胃炎などがないかを確認します。
<大腸内視鏡(大腸カメラ)>
下痢などの便通異常を伴う食欲不振や、大腸がんなどの大腸疾患が疑われた場合に行います
関連ページ:胃内視鏡(胃カメラ) 大腸内視鏡(大腸カメラ)
→ → → → →食欲不振外来top
4.治療は?
治療法は原因によって異なります。以下それぞれ簡単にまとめてみます。
A:心因性
心因性食欲不振の治療については原因となっているストレス環境の改善が大事ですが、仕事や家庭のストレスなどはすぐには改善するのが難しく、内服薬を使用して食欲不振の治療を行います。
ただし、うつ傾向などが強い場合には心療内科の先生と連携をとりながら改善を目指します。
B:機能性
機能性の食欲不振に対しては、低下した消化機能を補う薬(胃腸の動きを活発にする薬、消化剤、漢方など)を用いながら治療を行います。
治療を行いながら、消化機能を改善していくための生活習慣作りを行い食欲不振の根本治療も進めていきます。
また、胃の機能異常の原因の一つに胃内の常在細菌叢の変化が関わっているとの報告があり、胃内細菌叢を正常化させる成分を含んだ当院オリジナルのサプリi-katsuも治療の補助として使用することもあります。
C:器質性・症候性(病気によるもの)
病気による場合は原因となっている疾患(がん・甲状腺疾患など)を治療することで症状は改善してきます。
D:薬剤性
薬剤性の場合は通常は飲んでいる薬を中止したり変更すれば改善することがほとんどです。
ただ、抗がん剤のように簡単に中止できず薬の継続が望ましい場合には、胃薬や漢方薬などを併用しながら食欲不振を改善します。
→ → → → →食欲不振外来top
5.実際の治療例
- ケース① 50代 男性 食欲不振 体重減少
- ケース② 40代 男性 食べるとすぐ胃が張るのであまり食べたくない
- ケース③ 20代 女性 食欲がわかない
- ケース④ 40代 女性 胃が重い・食欲が出ない
- ケース⑤ 30代 女性 うつ病の治療中 食欲がわかない
- ケース⑥ 40代 女性 コロナワクチン接種後から食欲がわかない
【症状】
6か月ほど前から食欲がわかない、食べる気がしないとの症状があり、当初は高血圧症でかかりつけの内科に相談され、薬を出されて様子見となりました。
2か月ほど薬を飲んだものの症状が一向に改善せず、また体重もここ2か月で4kgほど減ったこともあり、心配され当院を受診されました。
【診察】
食欲不振に加え、体重減少もあることから何らかの病気が潜んでいる可能性があり、まずは腹部エコーの検査を行うことにしました
【検査】
食事を摂らずに来院されたので、当日すぐ腹部エコーを行い状態を確認しました。
膵臓に腫瘍(進行がん)を疑う所見を認めました。(写真の黄色矢印で囲まれた黒い領域)
【治療】
膵臓癌などの病気に伴う食欲不振は、原因疾患の治療が症状の治療になるため、早急にがん治療に特化した専門病院にご紹介しました。
【経過】
紹介先の病院でCTを行い膵臓癌と確定診断がつきました。
ステージⅢ期で放射線化学療法を行う方針となられ、同院で治療を行う方針となりました。
長期間にわたる食欲不振や短期間での体重減少を伴う食欲不振は、ガンなどの重大な病気による可能性があるため、なるべく早めに受診して頂き、少しでも病気が進む前に診断することが大切となります。
→ → → → →食欲不振外来top
② 40代 男性 食べるとすぐ胃が張るのであまり食べたくない
【症状】
数か月前から食事を摂ると胃がすぐに張ってしまう・お腹がいっぱいになってしまう感じが出てきて、症状がなかなか改善しないため近くの内科を受診。
ストレス性と言われ胃薬を処方されましたが、それでも改善がなく、次第に食べるのも何となく億劫になって食欲がなくなってきたとのことで当院を受診されました。
【診察】
触診では特に問題ありませんでしたが、受診された内科では特に検査はしておらず、血液検査・腹部エコー・胃内視鏡(胃カメラ)を行い原因となる病気があるかどうかを調べることにしました。
【検査】
検査上は血液検査・腹部エコー・胃内視鏡(胃カメラ)とも異常所見はなく、症状の原因は機能性ディスペプシア(食道や胃・十二指腸、その他の内臓に病気がないにも関わらず、胃の機能の異常で胃痛やもたれ・はり・食欲不振などが出る状態)と診断しました。
【治療】
症状からは機能性ディスペプシアでも胃排出の異常と胃適応性弛緩の異常を考えました。(胃排出とは食べた物を胃から十二指腸へ送ることであり、胃適応性弛緩とは食事のときに胃が拡張して食べ物を貯留する能力のことです。)
そこで胃の動きを改善させる内服薬と漢方を組み合わせて治療を開始し、また、合わせて食事のとり方の指導を行いました。
<治療内容>
1.消化管運動機能改善薬
胃の動きを改善する薬です。動きを正常化することで、胃の張りや食欲を改善します。
今回はアコチアミドという薬を選択しました。
2.漢方
漢方にも胃の動きを改善する作用や、それに加え摂食促進ホルモンであるグレリンの分泌を亢進させ食欲を改善させる作用があるものがあり1)、アコチアミドと併用をしました。
また、機能性ディスペプシアは改善後にも数ヵ月のあいだに5人に1人くらいが再発する2)といわれていますが、漢方を使用しながら胃の動きを正常化していくことで再発を起こしにくくしていきます。
3.生活習慣指導
仕事が忙しく食欲もないため、1日1食のみの生活となっていたため、ある程度時間を決めて食事を摂るようにして頂き、胃に動きのリズムを付けるようにするようにしました。
【経過】
内服を開始してしばらくは変化がなかったとのことでしたが、1週間ほどすると次第に食後の胃の張りが取れてきて食べられるようになってきて、2週間後の再診の際には食欲も少し出てきたとのことでした。
内服開始1か月目には症状は8割ほど改善し、2か月目の再診時には症状はなくなり食欲もあり、食事も以前のようにしっかりと取れる状態になっていました。
症状が出る少し前に転職し、ストレスや疲れがたまっており、今回の症状の要因と考えられました。治療で改善はしましたが、忙しい状況はしばらく続くとのことであり、漢方の方を継続し再発予防をしつつ、環境が安定したら漢方も中止する方針となっています。
※機能性ディスペプシアの詳細についてはこちらもご参照ください。
参考文献:1)Arai, M. et al. Hepatogastroenterology. 2012,59(113),p.62-66
2)Meineche-Schmidt V, Talley NJ, Pap A, et al. Impact of functional dyspepsia on quality of life and healthcare consumption after cessation of antisecretory treatment: a multicentre 3-month follow-up study. ScandJ Gastroenterol 1999; 34: 566-574
→ → → → →食欲不振外来top
【症状】
1か月ほど前から食欲がなく、食べてもすぐにお腹がいっぱいになる感じがあり、当院を受診されました。
【診察】
最近は胃痛も出てきたとのことで、触診ではみぞおちを押すと痛みがあり、上腹部の臓器(胃・膵臓など)の疾患から生じる食欲不振の可能性がありました。
腹部エコーや胃内視鏡(胃カメラ)検査もここ数年は受けていないとのことで、上腹部を調べる検査を行う方針としました。
【検査】
まず施行した腹部エコーでは、膵臓や胆のうといった上腹部の臓器には問題ありませんでしたが、胃壁の不整な肥厚を認め胃がんを疑いました。
実際に胃カメラを行うと、胃に腫瘍を認め、生検を行い病理診断で胃がんとの診断となりました。
ガンは潰瘍を伴い範囲が広く、深く進行していたため、痛みがでたり、胃の動きが制限されるためあまり食べられない・食欲不振といった症状が出ていたと考えられます。
【治療】
ガンは所謂スキルスタイプのもので、進行ガンであったため、速やかにガン拠点病院に紹介し治を行うこととなりました。
【経過】
ガンは進行がんであったものの手術可能な状態で、根治的な治療を受けることができました。
リハビリも順調に進み食事も順調にとれるようになられ、退院後は定期的に当院で経過を見ています。
胃がんは通常はピロリ菌が関連していることが多く、好発年齢は50歳以上ですが、中には未分化がんと呼ばれるピロリ菌がいない方にも生じるがんもあります。
このタイプは若年者の方にも生じることがあり、胃壁を這うように進行する所謂“スキルス”と呼ばれる胃がんです。
進行が早く見つかった時には手遅れになることもあり、食欲不振・胃痛なのどの症状がある際には早期に検査を受けることも重要です。
※関連ページ:胃がん
【症状】
以前は食事がありなんでも美味しく食べる方だったが、旦那さんがリモートワークとなり生活環境が変わり、何となく胃が重く、食欲が出なくなってきたとのことで、近医を受診され、胃カメラや血液検査・CTなどを受けたところ異常がなく、“精神的なもの”と言われ、胃薬を出されるもすっきりしないとのことで当院を受診されました。
【診察・検査】
前医にて必要な検査は行われておりその結果と問診から、機能性の食欲不振を考えました。
胃の重たさと食欲が出ないとの症状から、胃の動きの低下が考えられ、動きを改善する薬を錠剤や漢方を組み合わせて処方しました。
その後、2週間ほどで、胃の重たさや食欲は改善し薬はいったん中止としました。ご本人から症状をぶり返さないようにしたいとのことで、生活習慣や食事の指導を行いました。
また、漢方の萊菔子(ライフクシ)という生薬には胃に入った食物をスムーズに腸管に送り込む作用があり、その萊菔子(ライフクシ)を含んだ当院オリジナルのサプリ"i-katsu"を飲んで頂き、現在も以前のように食事を美味しく食べれる状態が続いています。
サプリは普段から飲んでいくことで、胃内環境の改善や胃酸分泌の正常化・胃の動きの促進効果により、胃の調子をよい状態のままキープしてくれます
【症状】
軽度のうつ病と診断され心療内科にて治療中の方。
うつ病自体は薬で安定しているものの、以前と比べて食欲がわかず、量も食べれないとのことで来院されました。
【診察】
食欲不振はうつ病からもおこりますが、現在は落ち着いているとのことで、消化器系や甲状腺などの他の病気の可能性や、薬の副作用などを考えました。
【検査】
まずは、実際に症状を起こすような病気がないかをチェックするため血液検査や腹部レントゲン・腹部エコー・胃カメラなどの検査を行いました。
腹部エコーでも肝胆膵などの上腹部の臓器に異常は認めず、また胃の中の病変のチェックのため胃カメラも行いましたが、ピロリ菌もなく、症状の原因となる病変はない状態でした。
血液検査でも甲状腺の異常などは認めませんでしたが、腹部レントゲンでは胃や大腸にガスの貯留を認めました。
【治療】
検査結果からは、病気というよりも向精神病薬の副作用による食欲不振を考えました。
向精神病薬の服用によって、胃や腸の動きが落ち、食欲不振や腹部のガス貯留が起こることがあります。
薬の副作用を考える場合、通常は内服の中止を検討することがほとんどですが、うつ病に対して使用している向精神病薬については、心療内科の主治医から「状態が安定してきているのでしばらくは継続する方がよい」とのことで、中止は難しい状態でした。
ですので、今回は心療内科の薬を継続したまま治療を行うこととし、前述のように胃の動きの低下といった機能の調整不良が薬の影響でおこるため、胃の機能改善薬などを用いて治療を行いました。
また、胃の動きを改善する漢方も有効なことが多いのですが、ご本人が漢方は飲みにくいのでできれば飲みたくないとのことで、胃の動きを改善する生薬を含んだ当院のオリジナルサプリ“i-katsu”を試してみることとしました。(サプリは錠剤なので服用できるとのことでした。)
<治療内容>
1.胃運動機能改善薬
胃の蠕動運動を促進することで、低下した機能を改善し食欲を回復させます。
2.サプリ
i-katsuの成分で生薬の生薬のダイダイ・萊菔子(ライフクシ)には、蠕動を促進し胃の動きを改善させ食欲を増進させる効果があります。
【経過】
治療開始後、徐々に食欲は出てきて、食べれる量も増えてきたとのことでした。
心療内科の薬もあるので、できれば薬はあまり飲みたくないとのことで、胃薬はいったん中止しサプリを継続してもらうこととしましたが、その後も食欲は維持できており、心療内科の薬は服用を続けつつ、サプリを併用し様子を見ています。
→ → → → →食欲不振外来top
【症状】
1週間ほど前に1度目のコロナワクチン接種を受けた方。ワクチン接種した日の夜に微熱が出現しましたが、翌日には改善。ただ、ワクチン接種後から何となく胃の気持ち悪さがあり、食欲もわかない状態が1週間ほど続いているとのことで来院されました。
【診察】【検査】
コロナワクチン(ファイザー・モデルナともに)の副作用に気持ち悪さや嘔気などの胃腸症状の報告があり、そこに起因する食欲不振を考えました。
ご本人がワクチンのアレルギーや何か病的な状態で起こっているのではないかと不安があられたので、念のため、血液検査や腹部エコー・レントゲン検査も行いましたが、いずれも異常はなく、対症的に治療を行っていく方針としました。
【治療】
薬やワクチンの影響などで胃や腸の動きが落ちると、胃酸がうっ滞や食事の停滞が起こり嘔気や食欲不振が生じることがあります。
ですので治療としては、胃や腸の動きを改善する薬を使い対応することとしました。
<治療内容>
1.胃の機能改善薬
胃の蠕動運動を促進することで、低下した機能を改善し食欲を回復させます。
2.漢方
漢方薬の中にも胃の動きを改善させたり、食欲ホルモンであるグレリンを刺激することで、食欲を増進させるものがあり、そちらも併用しました。
【経過】
薬を開始して数日で食欲は改善し、1週間後の再診の際には日程度で薬はいったんやめて経過を見ましたが、その後も安定した状態が維持できているとのことでした。
ワクチン接種が進むにつれ、接種後に胃腸症状や食欲不振が出る方が散見されています。症状が長引くと、その症状自体がストレスとなり、さらに症状を長引かせ慢性化することもあるため、胃腸症状や食欲不振が出て改善しない場合は早めに医療機関に相談することが重要です。
文責:神谷雄介院長(消化器内科・内視鏡専門医)
最終更新日 2023/2/14
→ → →ホーム
■関連ページ■
当院オリジナルサプリi-katsu 。胃・食道でお悩みの方はご覧ください
→ → → → → →ホーム