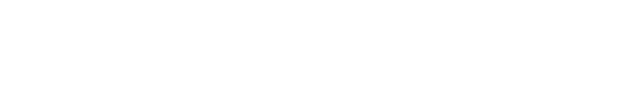過敏性腸症候群(IBS)
「通勤途中にトイレに駆け込みたくなる」「会議や試験の前にお腹が痛くなる」「下痢や便秘を繰り返して日常生活に支障がある」──
こうした症状は、過敏性腸症候群(IBS)の可能性があります。
腸に異常がないにもかかわらず、ストレスや生活習慣の影響で便通異常や腹痛を繰り返す病気で、
日本人の約10人に1人が悩んでいると言われています。
この記事では、過敏性腸症候群の原因や症状、検査・治療方法を、当院での実際の症例を交えて解説します。
「診察や検査を受けた方がいいのか?」と迷っている方も、ぜひご参考ください。
お電話でのご相談・ご予約は03-5940-3833
1.過敏性腸症候群とは?その原因は?
過敏性腸症候群(Irritable Bowel Syndrome: IBS アイビーエス)とは、
腸に異常がないにもかかわらず、慢性的な腹痛や便秘・下痢などの便通異常を繰り返す疾患
です。
もともと腸の運動は自律神経やセロトニンというホルモンが調整しています。
不安や緊張といった心因的ストレスや、不規則不摂生な生活・過労や気候の変化などの環境的なストレスが続くと、
- 自律神経がうまく働かなくなったり、
- 腸の粘膜からセロトニンが過剰に分泌されたりすることで、
腸の運動の調整がうまくいかなくなり過敏性腸症候群が発症するのではないかと考えられています。
また最近では感染性胃腸炎(いわゆる食あたり)後に過敏性腸症候群を発症する方がおられることもわかってきています。
■ストレスと腸・脳の関係■
先ほど述べたように、脳がストレスを感じると自律神経の働きや腸の機能を調整するセロトニンの分泌が乱れ、腸の運動異常や知覚過敏などが起こります。
また、そうすることで起こる腸の不快感や痛みや便通異常がストレスとして脳に伝わり、さらに症状が悪化するという悪循環に陥りやすくなってしまうのです。
【ストレスの例】
・通勤電車などのトイレに行くことのできない状況で腹痛や下痢が起きたらどうしようという恐怖感(予期不安)によるストレス
・新社会人になったり、進級・進学によって学校の環境が変わったり、仕事の内容が変わったりといった環境の変化などのストレス
・仕事の疲れや寝不足、風邪、夏バテなどの身体的なストレス
※同じようなストレス環境下でも過敏性腸症候群を発症する人・しない人がいるのは、ストレスに対しての耐性や腸内細菌叢の状態などの体質的な部分も関わってきます。
2.症状は?
・腹痛、腹部違和感
・下痢、便秘、または便秘と下痢を繰り返すなどの便通異常
・お腹のはり
・お腹がゴロゴロと鳴る
・残便感、頻便感
・急にくる便意
などが過敏性腸症候群では起こります。
特にストレスで増悪したり、通勤・通学途中のトイレに行けない場面や会議前・試験前などの緊張する場面での腹痛・便意などが過敏性腸症候群ではよく見られます。
3.検査・診断は?
症状自体は便通異常や腹痛といった過敏性腸症候群に合致する場合でも、
- 炎症性腸疾患と呼ばれる慢性の腸炎
- 大腸がん
- 甲状腺疾患
といった別の病気が原因の場合もあります。
ですので、他の疾患を血液検査・レントゲン・腹部エコー検査・大腸内視鏡(大腸カメラ)などの検査で除外していく必要があります。
■関連ページ:過敏性腸症候群が治らないと思ったら潰瘍性大腸炎だった症例
血液検査:
炎症などの数値、甲状腺疾患の数値などを確認します。
レントゲン:
腸管のガスの状態や便の溜まり具合などを確認します。
腹部エコー:
小腸や大腸の粘膜の浮腫みや炎症、進行がんなどがないかを外から見てみます。
大腸内視鏡(大腸カメラ):
過敏性腸症候群の診断において一番大切な検査になります。
腹部エコーやレントゲンなどで実際に大腸の病気が疑われる場合や、また他の検査で異常がなくても治療で改善がない場合には大腸内視鏡を行います。
実際に大腸の粘膜の状態を直接見ることが出来、炎症性腸疾患やガンなどの有無、腹部エコーやレントゲンではわからないような粘膜の詳細な状態を調べ過敏性腸症候群かどうかを診断します。
お電話でのご相談・ご予約は03-5940-3833
4.治療は?
過敏性腸症候群の原因の多くはストレスですが、仕事や家庭のストレスなどはすぐには改善するのが難しいため、
症状を起こさないようにする食事療法や内服治療、体質を改善しストレスに負けない腸を作る漢方薬などを用います。
◆食事療法◆
脂っこい食事・刺激物を控える
唐揚げ、ラーメン、唐辛子、アルコール、カフェインなどは腸を刺激しやすい。
水溶性食物繊維を取り入れる
海藻、オートミール、バナナなどは便通の安定に有効。
低FODMAP食
近年注目されているのが低FODMAP食です。
FODMAPとは発酵性の糖質を指し、小腸で吸収されにくく大腸でガスを発生させやすい特徴があります。
低フォドマップ食を取り入れた過敏性腸症候群の患者さんの約70%で症状が改善したとのデータも上がっています。
|
分類 |
食べてよい食品 |
控えた方がよい食品 |
|
穀類 |
米、そば、オートミール |
小麦、大麦、ライ麦 |
|
野菜 |
にんじん、なす、トマト、レタス、きゅうり |
玉ねぎ、にんにく、カリフラワー、マッシュルーム |
|
果物 |
いちご、みかん、ぶどう、バナナ |
りんご、梨、スイカ、マンゴー |
|
たんぱく質 |
肉、魚、卵、豆腐(木綿) |
大豆製品(納豆、豆乳など) |
|
乳製品 |
ラクトースフリー牛乳、アーモンドミルク |
牛乳、ヨーグルト、ソフトチーズ |
|
その他 |
– |
人工甘味料(ソルビトール、マンニトールなど) |
■関連ページ:低フォドマップ食による過敏性腸症候群の治療方法と実際の治療例
◆内服薬◆
過敏性腸症候群に対しての治療薬は色々と種類があり、便の状態(下痢型・便秘型)や腹痛の部位などによって薬を組み合わせていきます。
当院では、漢方薬なども使用し、過敏性腸症候群になりやすい体質自体の改善にも取り組んでいます。
セロトニン3受容体拮抗薬(薬品名:イリボー)
下痢型の過敏性腸症候群の原因と言われる腸内のセロトニンの作用を抑え、下痢症状を抑えます。
高分子重合体(薬品名:コロネルなど)
便に含まれる水分量を調整して、便の性状をちょうどよい形にします。
消化管運動調整薬(薬品名:セレキノンなど)
消化管の動きを抑えたり、活動性を上げたりします。
乳酸菌製剤(薬品名:ビオフェルミン・ビオスリーなど)
いわゆる整腸剤です。腸内細菌のバランスを整え腸の動きを正常化させます。
漢方薬(薬品名:桂枝加芍薬湯・大建中湯・半夏瀉心湯・人参湯など)
知覚過敏や運動異常になりやすい体質を改善します。またお腹の冷えなども改善し、働きを正常化させます。
抗不安薬(薬品名:デパスなど)
過敏性腸症候群の原因として不安要素が大きい場合に他の薬と併用します。
例えば、「トイレに行けない電車の中で便意を感じたらどうしよう」という不安感から、お腹の痛みや下痢が誘発されるような方には有効なことがあります。
5.実際の治療例
Case① 30代男性 慢性的に下痢が続く
【症状】
大学卒業後、社会人になってから下痢気味になり、数年前から悪化し、1日5-6回の下痢があり会社でも度々トイレに行かなくてはならず、またここ最近は下腹部の痛みも出てきたとことで来院されました。
【検査】
経過が慢性的であり、ご本人も大腸がんなどの病気がご心配とのことであり、大腸内視鏡(大腸カメラ)や血液検査で病気が潜んでいないかを確認しました。
結果は特に問題なく、下痢型の過敏性腸症候群と診断しました。
【治療】
仕事によるストレスがあるものの環境をすぐに変えることは難しいので、過敏性腸症候群の症状をコントロールし上手く付き合っていくため以下の治療を行いました。
①食生活の改善
・減酒
アルコールには便を緩くしてしまう作用があります。この方はお酒をほぼ毎日飲まれていたので、休肝日をしっかりつくり、翌日仕事のない週末に飲むようにしていただきました。
②内服治療
・セロトニン3受容体拮抗薬(イリボー)
下痢型の過敏性腸症候群の方にはかなり効いてくれるお薬です。
ただ量によってはお腹の張りなどの副作用が出てしまったり、やめると症状が再燃することが多いため、過敏性腸症候群の体質を変えていくような整腸剤と漢方薬を併用しました。
・整腸剤
腸内細菌のバランスを整えることで、便通や知覚過敏の改善が期待できます。
・漢方薬(桂枝加芍薬湯)
腹痛に対しての処方です。腸の過蠕動(動きすぎ)や知覚過敏に対して効果があり、知覚過敏などの体質も改善してくれる効果があります。
・抗不安薬
特に会議前や訪問先に向かう途中などプレッシャーがかかる場面では必ず下痢と腹痛をおこすとのこともあり、そのような場面では眠気の来ないような軽い抗不安薬を屯用することとしました。
【経過】
薬を飲み始めて2-3日で下痢は減り、腹痛も出にくくなりました。飲み始めて2週間目の再診時には「ほぼ下痢は落ち着いており、腹痛が時々出る」と言う状況でした。
さらに1か月程経過したころには症状がほとんど気にならないところまで改善されました。
その後は漢方をベースに処方を続け、現在は調子が悪くなったらセロトニン3受容体拮抗薬を数日飲んで落ち着ける、プレッシャーがかかるときに抗不安薬を頓服して症状が出ないようにする、といったような具合で薬を減薬して症状とうまく付き合って頂いています。
【院長からのコメント】
薬を減らしても大丈夫になった理由としては、漢方や整腸剤による体質改善に加え、「下痢や腹痛になったらどうしよう」ということがストレスとなり、それがまた腸に影響するという悪循環に陥ってたため、下痢・腹痛が落ち着いたことで不安要素が改善され、結果減薬していくことにつながったと考えられます。
お電話でのご相談・ご予約は03-5940-3833
Case② 30代 女性 下腹部痛
【症状】
学生時代から腹痛が出やすい体質でしたが、我慢できる程度だったので特に検査や治療は受けずに様子を見ていました。
ここ数か月間、下腹痛が出てくる頻度が増加し、まず婦人科を受診されましたが異常はなく、消化器内科での診察を勧められ当院を受診されました。
【診察】
診察時には特に痛みはありませんでしたが、特に食後に症状が出ることが多いとのことでした。
婦人科では異常がないとのことで、腹部レントゲン・腹部エコー・大腸カメラなどの検査を行い消化器疾患の有無をチェックすることとしました。
【検査】
腹部レントゲンでは異常ガスなどはなく、腹部エコーでも痛みの原因となる疾患は認めませんでした。
また、大腸内視鏡も行いましたが、異常は認めず問題ない状態でした。
婦人科でも消化器でも問題は認めないため、過敏性腸症候群による腹痛と考えました。
【治療】
症状のきっかけは特に感じてなかったものの、転職を契機に生活のリズムが変わったり、慣れない仕事にストレスを感じることが多かったのが原因かもしれないとのことでした。
現在はだいぶ仕事に慣れてはきたものの、下腹部痛がストレスとなっているとのことで、痛みによるストレスが腸の知覚を過敏にしさらに痛みを感じさせるという悪循環になっていると考えられました。
治療としては、知覚過敏を抑える漢方や整腸剤を使用し経過を見ることとしました。
■治療内容■
・整腸剤
腸内細菌のバランスを整えることで、便通や知覚過敏の改善が期待できます。
・漢方薬(人参湯)
食後に症状が出やすいとのことで、食後の腸の蠕動を適度に保ち知覚過敏やお腹の冷えからくるような痛みに効果があります。
【経過】
薬を飲み始めて1週間ほどすると下腹部痛が出現する頻度が減ってきて、痛みが出たときも程度がそれほど強くないような状態になり、1か月ほど薬を続けて頂くと下腹部痛はほぼなくなったとのことでした。
その後は症状が出た時だけ服用して頂くこととしましたが、落ち着いた状態が続いておられます。
この方も、前の方と同じように「症状がストレスになりさらに症状を起こす」という状態であったため、症状の改善とともに安定した状態になったと考えられます。
ただし、痛みがある場合は、過敏性腸症候群ではなく、婦人科疾患や大腸憩室炎などの他の病気の可能性ももちろんあるため、しっかりと検査で状況を見極めた上で治療を行う必要があります。
Case③ 20代 男性 過敏性腸症候群が治らない
【症状】
数年前から一日数回の下痢と腹痛があり、近医にて過敏性腸症候群と診断され投薬治療を受けていましたが、症状が改善しないととのことで当院を受診されました。
【診察】
下痢や腹痛はストレス時に悪化するとのことであり過敏性腸症候群の症状としても矛盾はありませんでしたが、
潰瘍性大腸炎やクローン病などの慢性的に腸に炎症を起こす炎症性腸疾患も否定はできない症状でした。
前医では特に検査はせずに症状のみで過敏性腸症候群と診断を受けたとのことで、ご本人と相談し大腸内視鏡検査を行い腸の状態を確認してみることとしました。
【検査】
大腸内視鏡行うと大腸全体に広がる炎症を認めました。
生検を行い内視鏡所見と合わせて潰瘍性大腸炎と診断しました。
大腸内視鏡画像です。 大腸粘膜全体に潰瘍性大腸炎と思われるびらん(黄色矢印部分)・炎症によるうっ血(青丸部分)を認めました。
【治療】
潰瘍性大腸炎とは、「体内に侵入したウイルスや細菌などの外的を攻撃する免疫細胞(白血球など)が、大腸粘膜や腸内細菌を敵と誤認して攻撃してしまい、大腸の粘膜に慢性的に炎症を起こす病気」です。
大腸に炎症を来すことで、腹痛・下痢・血便などの症状を来します。
実は根本的な治療法が今のところはない難病の一つですが、炎症自体は薬で抑えることが可能で、継続的に薬を使っていく必要があります。
今回も患者さんにご説明し、投薬治療を開始しました。
※詳細は「潰瘍性大腸炎」をご参照ください。
<治療内容>
潰瘍性大腸炎に対しての抗炎症薬(5-ASA)製剤の投与
【経過】
治療開始すると1週間ほどで下痢・腹痛はかなり改善し、2週間ほどで腹痛は消失し、通常便になりました。
状態的には薬で症状が消えた状態=寛解状態となりました。
ただ、先述のように根本的な治療法はなく薬で炎症を抑えているだけであり、この寛解状態を維持するため投薬を継続しています。
(やめると高確率で再燃してしまいます。)
【院長からのコメント】
過敏性腸症候群はストレスや緊張で悪化しやすいのが特徴ですが、
潰瘍性大腸炎も同じように腹痛や便通異常をきたし、かつストレスで増悪することもあり、
症状が合致するからと言って必ずしも過敏性腸症候群とは言えません。
今回のように症状が治らない場合はもちろん、過敏性腸症候群と診断する際にはしっかりと大腸内視鏡などの検査することが重要です。
お電話でのご相談・ご予約は03-5940-3833
6.過敏性腸症候群のQ&A
A:感染性胃腸炎(食あたり)なども原因になります。
感染性胃腸炎を起こした後に約10%程度の方に発症し、実は過敏性腸症候群の1/6程度は感染性胃腸炎が要因となっており、少なくとも胃腸炎後2-3年は過敏性腸症候群の発症のリスクが高いという研究結果があります
胃腸炎後に過敏性腸症候群を起こしやすくなるリスクとしては、女性・若年・心理的問題・胃腸炎自体の程度が強いことが関連していると言われています。
胃腸炎後の過敏性腸症候群は、胃腸炎が治っていないと誤診されてしまうことも多く、適切な治療を受けれずにいつまでも症状に悩ませることもあるため、胃腸の専門施設でしっかりと診断を受けることが大切です。
参考文献;Longstreth GF, Hawkey CJ, Mayer EA, et al. Characteristics of patients with irritable bowel syndrome recruited from three sources: implications for clinical trials. Aliment Pharmacol Ther 2001; 15: 959-964
Thabane M, Kottachchi DT, Marshall JK. Systematic review and meta-analysis: the incidence and prognosis of post-infectious irritable bowel syndrome. Aliment Pharmacol Ther 2007; 26: 535-544
Barbara G, Grover M, Bercik P, et al. Rome foundation working team report on post-infection irritable bowel syndrome. Gastroenterology 2019; 156: 46-58.e7
A:遺伝が関与することが分かっています。
決定的な原因遺伝子はまだ解明されてないものの、セロトニン関連遺伝子や腫瘍壊死因子 TNFSF15 遺伝子と 過敏性腸症候群 の関連があることが分かっています。
今後原因遺伝子の解明が進み、過敏性腸症候群の新たな治療法ができることも期待されています。
参考文献:Czogalla B, Schmitteckert S, Houghton LA, et al. A meta-analysis of immunogenetic Case-Control Association Studies in irritable bowel syndrome. Neurogastroenterol Motil 2015; 27: 717-727
Q:過敏性腸症候群の診断に大腸内視鏡(大腸カメラ)は必要ですか?
A:基本的には必要と考えます。
過敏性腸症候群の代表的な症状である「腹痛や下痢・頻便感・お腹の渋り感」などは、大腸がん・潰瘍性大腸炎やクローン病といった炎症性腸疾患などの他の病気でも起こりうるため、大腸内視鏡を行い否定しておくことが重要です。
実際に過敏性腸症候群 が疑われている患者さんに大腸内視鏡を行うと約30%に何らかの器質疾患が見つかったというデータもあります。
症状が似ていても、過敏性腸症候群とほかの病気では治療内容が全く異なり、特に大腸がんや炎症性腸疾患は進行性に悪化するため、症状がある場合にはまずはきちんと検査を行いましょう。
参考文献:Gu HX, Zhang YL, Zhi FC, et al. Organic colonic lesions in 3,332 patients with suspected irritable bowelsyndrome and lacking warning signs, a retrospective case: control study. Int J Colorectal Dis 2011; 26: 935-940
お電話でのご相談・ご予約は03-5940-3833
A:しっかりした治療を行っていくことで治療することは可能です!
過敏性腸症候群によって引き起こされる腹痛・下痢などの症状は投薬治療にて抑えていくことができます。
また発症にはストレスが関わってくるので、ストレス因子を改善することも大切です。
職場環境や家庭環境がなかなか変わらない場合は、投薬治療などで症状をコントロールしうまく付き合っていけるような状態を作っていきます。
また、過敏性腸症候群による腹痛や下痢などを抑えることで、症状によるストレスや不安感が軽減され、結果過敏性腸症候群よくなるというパターンも多くみられます。
お電話でのご相談・ご予約は03-5940-3833
医師紹介
神谷雄介(かみや ゆうすけ)院長
📍経歴
国立佐賀大学医学部卒業後、消化器内科・内視鏡内科の道を歩み始め、
消化器・胃腸疾患の患者さんが数多く集まる戸畑共立病院・板橋中央総合病院・平塚胃腸病院にて研鑽を積む。
胃もたれや下痢といった一般的な症状から炎症性腸疾患や消化器がん治療まで幅広く診療を行いながら、
内視鏡専門医として年間3000件弱の内視鏡検査、および早期がんの高度な内視鏡治療まで数千件の内視鏡治療を施行。
2016年4月に巣鴨駅前胃腸内科クリニックを開業。
内視鏡検査だけでなく、胃痛・腹痛・胸やけや便秘などの胃腸症状専門外来や、がんの予防・早期発見に力を入れ、診療を行っている。
- 日本内科学会認定医
- 日本消化器病学会専門医
- 日本消化器内視鏡学会専門医
🩺 診療にあたっての想い
胃や大腸の病気は、早期発見・早期治療がとても重要です。
「気になるけれど、どこに相談したらよいかわからない」「検査は怖いし、つらそうで不安」
そんな方にも安心して診察や検査を頂けるうような診療を心がけております。お気軽にご相談ください。
アクセス
所在地
〒170-0002
東京都豊島区巣鴨1丁目18-11 十一屋ビル4階
交通
巣鴨駅から徒歩2分、ローソン(1F)の4階巣鴨駅前胃腸内科クリニック
お電話での予約・お問い合わせ:03-5940-3833
文責:巣鴨駅前胃腸内科クリニック院長 神谷雄介
(消化器学会・内視鏡学会専門医)
■関連ページ■
・大腸がん
・エコー
・大腸カメラ(大腸内視鏡)『痛くない!無痛内視鏡検査』