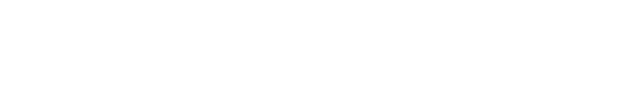感染性腸炎(急性胃腸炎)
急な嘔吐や下痢で「食中毒かな?」「感染したかも?」と不安になっていませんか?
感染性腸炎は、細菌やウイルスが原因で誰にでも起こり得る身近な病気です。
多くは数日で回復しますが、O-157やカンピロバクターなどでは重症化することもあり注意が必要です。
当院では、腹部エコーや血液検査などを組み合わせて正確に診断し、適切な治療を行っています。
WEB予約・電話予約を受け付けていますので症状がある方は、ぜひ早めにご相談ください。
感染性腸炎とは?
感染性腸炎とは、細菌やウイルスなどが口から入ることによって起こる腸炎です。
嘔吐や下痢を伴うことが多く「嘔吐下痢症」と呼ばれたり、急激に発症することから「急性胃腸炎」などと呼ばれることもあります。
身近なものであると、カキなどの2枚貝を食べた後に起こる「ノロウイルス」による嘔吐下痢症も感染性腸炎の中の一つです。
原因は?
①食中毒
汚染された食物を十分な加熱なしで食べてしまうと、付着している菌やウイルスから感染します。
・焼肉(大腸菌など)
・焼き鳥(カンピロバクター)
・カキ(ノロ)
・魚介類(ビブリオ)
・痛んだおにぎりや弁当(ブドウ球菌)
また、海外の途上国の水なども注意が必要です。
②人からの感染
感染者の吐物や下痢などから移ってしまうことがあります。
ですので、ご家族や会社で共用のトイレの使用、トイレ後のタオルの共用などは注意が必要です。
また、ウイルスや菌が手についた状態で調理した料理などからも感染することはあり、手洗いもしっかりと行う必要があります。
症状は?
・吐き気・嘔吐
・下痢(軟便~水様性)
・時に腹痛・発熱・血便
菌やウイルスの潜伏期間があるため、早いもので2時間・長いものだと1週間経ってからの発症することもあります。
黄色ブドウ球菌:2-3時間 ビブリオ:6-12時間 ノロ:1-2日 大腸菌(O-157など):2-5日 カンピロバクター:2-7日
検査・診断法は?
血液検査:
腸炎の炎症の程度を調べます。当院では1時間以内に結果がわかります。
腹部エコー・レントゲン:
腸管の浮腫んでいる部位や状態を見て感染菌やウイルスを予想します。
また、他の腸炎(虚血性腸炎や潰瘍性大腸炎・クローン病など)の可能性がないかのチェックも行います。
■実際の腸炎の画像所見
エコーで上行結腸に全周性壁肥厚を認めました。範囲は広範で、特に粘膜下層の肥厚が目立つため、全体的に白っぽく描出されています。
問診で3日前に鶏肉を食べたというお話と、エコー所見からカンピロバクター腸炎を考え治療を行いました。
便培養:
便中の菌を調べる検査です。検査結果に1週間かかりますが、症状が長引きそうなときやO-157などの激しい腸炎の時は有効です。
大腸内視鏡(大腸カメラ):
直接大腸の状態を見て状態を評価します。
感染性腸炎の際にはいきなり大腸内視鏡を行うことは少ないですが、以下の場合には内視鏡を行うことがあります。
- エコー検査で感染性腸炎以外の腸炎(虚血性腸炎や潰瘍性大腸炎・クローン病など)を疑った場合
- 血便を伴う場合
- 症状が改善しない場合
実際に他院で感染性腸炎と診断され治療を受けても改善なく、検査してみると虚血性腸炎だったというケースもあります。
▶関連ページ
・【実際の治療例】「急性胃腸炎」と診断されたが治らない腹痛と血便…実は虚血性腸炎だった
治療は?
症状は3-4日で落ち着くことがほとんどです。
ただ、O-157やサルモネラ、カンピロバクターなどは時に重症化することがあり、そのような菌の感染が疑われた場合には慎重に経過を診ます。
※治るまでの目安 : 黄色ブドウ球菌:吐き気中心で1-2日 ノロ:1-3日 ビブリオ:2-3日 カンピロバクター:2-5日 O-157:5-7日
治療内容
・安静
・水分摂取(OS-1、スポーツドリンク)や点滴
・薬(吐き気止め・軽い下痢止め 整腸剤)
・抗生剤(細菌感染を疑うとき)
・食事制限(消化の良いもの:おかゆ、素うどん、ゼリーやプリン、果物など)
予防は?
① 手洗いをしっかり!
-
外から帰ったあと
-
トイレのあと
-
食事の前
-
調理前・調理中 👉 石けんと流水で30秒以上洗いましょう。
② 食べ物の衛生に注意!
-
生肉や魚はよく加熱(中心部75℃以上)
-
生野菜はよく洗う
-
調理器具(まな板・包丁など)は肉と野菜で分ける
-
食べ物はすぐ冷蔵・冷凍して保存
③ 水分の管理も大事
-
旅行先では水道水を避ける(特に海外ではミネラルウォーターを)
-
氷にも注意(現地の水道水で作られた氷が原因になることも)
④ ノロウイルスなどの感染対策
-
感染者の嘔吐物や便の処理は手袋・マスクを使用し、塩素系漂白剤で消毒
-
洗濯物も85℃以上で加熱・洗濯
⑤ 感染性腸炎の時は調理を避けて
-
調理する人から他の人にうつる危険が! 👉 下痢・嘔吐があるときは、料理は休みましょう。
💡こんな時は早めの受診を!
-
下痢が長引く
-
血便が出る
-
高熱や激しい腹痛がある
-
脱水症状(口の渇き・尿が出ない・めまい)
当院ではWEB予約・電話予約を受け付けています。症状が強い場合や心配なときは、我慢せずにご相談ください。。
📞 お電話でのご予約:03-5940-3833
実際の治療例
①20代男性|腹痛・嘔吐・下痢
【症状】
前日夜からの突然の腹痛と嘔吐・下痢を主訴に来院されました
【診察】
触診では臍中心に痛みがあり、前日に貝を食べたとのことからウィルス性の小腸炎を疑い検査を行いました。
【検査】
腹部レントゲンで小腸ガスを認め、腹部エコーでは小腸液の貯留と浮腫みを認め、小腸炎と診断しました。
【治療】
ウィルス性の小腸炎は、ウィルスに直接効果のある薬はなく、症状を和らげる薬を使いつつ、自己免疫でウイルスが排除されるのを待つ、という形になります。
基本的には吐き気は半日程度で落ち着き、下痢や腹痛も2-3日で落ち着くことが多いです。
①内服治療;整腸剤 漢方薬
嘔気・嘔吐・下痢・腹痛といった胃腸炎症状を和らげます。
②食事指導
小腸が炎症を起こしている間は食べ物の消化吸収や通過がうまくいかず嘔吐や下痢を起こします。そのため食事も生ものやアルコールをさけ、消化しやすいものを召し上がっていただきました。
【経過】
受診後、昼と夕方に服薬をすると、嘔気は消え腹痛もかなり和らいぎ、翌日には下痢の回数も半分ほどとなり、3日目にはほぼ改善したとのことでした。1週間後の再診の際には症状は完全に改善しており、終診としました。
②40代 女性 腹痛・下痢が治らない
【症状】
5日ほど前に発熱と腹痛と水下痢があり、翌日に近くの内科を受診し胃腸炎と診断され整腸剤の処方となりましたが、全然治らないとのことで当院を受診されました。
【診察】
触診では下腹部に痛みがあり、水下痢はまだ1日10回以上続いている状態でした。
発熱を伴っていたこと・症状が長引いていることなどから細菌性の感染性腸炎を疑いました。前医では特に検査をしておらず、腹部エコーやレントゲン・血液検査で状態を評価してみることとしました。
【検査】
腹部エコーで右大腸中心に炎症像および血液検査にて炎症反応の上昇があり、中等度の大腸炎と診断しました。
上行結腸の画像です。 水色矢印の範囲で腸管が浮腫み 粘膜下層が炎症で白く見えます (黄色矢印)
【治療】
右中心に起こる急性の大腸炎はカンピロバクターや病原性大腸菌による細菌感染が多く、主に食中毒が原因となります。
食中毒の場合は潜伏期間があり、食べてすぐ発症することもあれば1週間くらいたってから発症する場合もあります。
今回も問診で確認すると、最初に症状がでた日の4日前に鶏の刺身を食べたとのことで、カンピロバクター腸炎を考え治療を行いました。
①内服治療;整腸剤 漢方薬
下痢・腹痛といった胃腸炎症状を和らげます。
②抗生剤
菌を倒すために使用します。細菌性の腸炎に対して、炎症反応や症状が強い場合に用います
③食事指導
大腸炎の場合は水分が吸収できずに激しい水下痢を起こしてしまいます。そのため水分摂取はOS1やポカリスエットなどの体に吸収されやすいもの、食事はおかゆなどの消化しやすいものを召し上がっていただきました。
【経過】
受診後2日ほど症状が続きましたが、3日目くらいから次第に和らぎ5日後に再診頂いた際にはほぼ改善している状態で、整腸剤を数日間継続していただく形で終診となりました。
細菌性の腸炎は症状も激しく長引くことが多く、また激しい胃腸炎後は過敏性腸症候群になるリスクがあることが分かっており1)、発症初期段階でしっかりと診断し適切な治療を行うことが大切です。
まとめ
-
感染性腸炎はウイルスや細菌が原因で、嘔吐・下痢・腹痛を伴います
-
多くは数日で回復しますが、重症化するケースもあるため注意が必要です
-
検査で他の腸疾患との鑑別も重要
-
早めの診断・治療が合併症予防につながります
👉 不安な症状がある方は、当院のWEB予約からご相談ください。
お電話でのご相談・ご予約は03-5940-3833
よくある質問FAQ
Q:感染性腸炎は市販薬で治せますか?
A:軽症であれば水分補給と整腸剤などで改善することもありますが、細菌性腸炎では抗生剤が必要になる場合もあります。自己判断せず受診をおすすめします。
Q:どのくらいで治りますか?
A:ウイルス性は2〜3日、細菌性は5〜7日かかることもあります。改善しない場合は精密検査が必要です。
Q:人から人に移りますか?
A:移る場合があります。
感染性腸炎の原因は、病原体が口から入ってきて起こる“経口感染”で発症します。大部分は食品から感染する食中毒ですが、以下の場合などに人から移る場合もあります。
・感染者の吐物や便に触れた手で口元を触ったりする場合
感染者の吐物や糞便を処理する際に、手についてしまい、手洗いが不十分だと、病原体が口に入ってしまい感染することがあります。
・感染者の手洗いが不十分な場合
病原体が手に付着したまま共有のタオルやドアや家具を触れ、その病原体を付着したものを他の人が触れ、そこから口を触りにうつるケースも考えられます。
また、感染者が手洗い不十分な状態で食品を触ったり、調理を行い、それを食べてしまうことで発症することもあり得ます。
・病原体が舞い散る場合。
感染者の便や吐物を放置し乾燥させてしまうと、病原体が空気中に舞い散ってしまい、その空気を吸い込むことで感染することもあります。
Q:仕事はできますか?
A:内容によって変わってきます。
通常の感染性腸炎の場合は、法律上の就労停止などはありませんが、しっかり休養を取った方が体調面ではよいと思われます。
ただし、飲食業や食品関係の仕事について国からの指示として、
「責任者に対し“直に調理、加工、製造する者(食品取扱者)”に嘔吐下痢などの症状があれば、感染性胃腸炎の有無を確認すること。ノロウイスを原因であった場合は、 リアルタイムPCR等の好感度の検便検査でノロウイルスを保有していないことが確認されるまで、食品の取り扱いに従事させないよう処置をとることが望ましい」
と指導していますので、基本的には症状が改善し、病原体が消失するまでは休養が必要と考えます。
※ノロウイルスなどのウイルス検査は保険診療外となるため当院では対応していません。
Q:感染性腸炎の時に食べてよいものは?
A:おかゆ・うどん・ゼリー・プリンなど、消化の良い食品がおすすめです。生もの・揚げ物・アルコール・乳製品は避けてください。
Q:熱があるときはどうすればいいですか?
A:解熱剤の使用は控えめにし、しっかり水分補給をしてください。高熱やぐったりする場合はすぐに医療機関を受診してください。
Q:感染性腸炎のあとに過敏性腸症候群(IBS)になることがありますか?
A:はい。感染性腸炎後に腸の過敏状態が続き、下痢や腹痛が長引く「感染後IBS」になることがあります【参考文献1】。
医師紹介
神谷雄介(かみや ゆうすけ)院長
📍経歴
国立佐賀大学医学部卒業後、消化器内科・内視鏡内科の道を歩み始め、
消化器・胃腸疾患の患者さんが数多く集まる戸畑共立病院・板橋中央総合病院・平塚胃腸病院にて研鑽を積む。
胃もたれや便通異常といった一般的な症状から、炎症性腸疾患や消化器がん治療まで幅広く診療を行いながら、
内視鏡専門医として年間3000件弱の内視鏡検査、および早期がんの高度な内視鏡治療まで数千件の内視鏡治療を施行。
2016年4月に巣鴨駅前胃腸内科クリニックを開業。
内視鏡検査だけでなく、胃痛・腹痛・胸やけや下痢などの胃腸症状専門外来や、がんの予防・早期発見に力を入れている。
- 日本内科学会認定医
- 日本消化器病学会専門医
- 日本消化器内視鏡学会専門医
🩺 診療にあたっての想い
胃や大腸の病気は、早期発見・早期治療がとても重要です。
「気になるけれど、どこに相談したらよいかわからない」「検査は怖いし、つらそうで不安」
そんな方にも安心して診察や検査を頂けるうような診療を心がけております。お気軽にご相談ください。
アクセス
所在地
〒170-0002
東京都豊島区巣鴨1丁目18-11 十一屋ビル4階
交通
巣鴨駅から徒歩2分、ローソン(1F)の4階巣鴨駅前胃腸内科クリニック
JR巣鴨駅 南口より徒歩3分。詳しい道順はこちら
▶📞お電話での予約・お問い合わせ:03-5940-3833
▶【WEB予約】
関連ページ
参考文献リスト
-
Barbara G, Grover M, Bercik P, et al. Rome Foundation working team report on post-infection irritable bowel syndrome. Gastroenterology. 2019;156:46-58.e7.
-
日本消化器関連学会「過敏性腸症候群ガイドライン2020」
-
一般社団法人日本感染症学会,公益社団法人日本化学療法学会. JAID/JSC感染症治療ガイドライン2015 ―腸管感染症―. 感染症誌. 2015;90:31-65
文責:巣鴨駅前胃腸内科クリニック院長 神谷雄介
(消化器学会・内視鏡学会専門医)