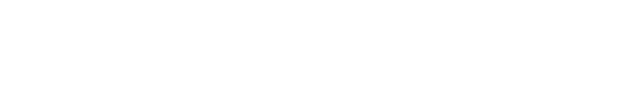なぜ逆流性食道炎は治らないのか?ぶり返すのか?|専門医が原因と治療を解説
「逆流性食道炎がなかなか治らない」「一度良くなってもすぐにぶり返す」——
外来でもよく伺うお悩みです。
なぜ治りにくく、再発しやすいのか。
原因と治療の考え方を、消化器内科専門医の院長がわかりやすく解説します。
必要に応じて検査・治療まで当院で一貫対応いたします(鎮静下の無痛内視鏡にも対応)。
お悩みの方はぜひご相談ください。
▶【WEB予約】
▶お電話:03-5940-3833
そもそも逆流性食道炎とは?その症状や原因は?
「なぜ逆流性食道炎は治らないのか?ぶり返すのか?」を考えるためには、
そもそも「なぜ逆流性食道炎が起こるのか」という原因を考える必要があります。
逆流性食道炎とは胃酸が胃から食道に逆流し、胃と食道のつなぎ目の部分に炎症が起きている状態です。
胃の粘膜はもともと胃酸に対して耐性をもっており、胃酸によって傷つかないようになっています。
しかし食道にはそのような耐性がないため、胃酸が逆流すると粘膜が傷ついて炎症を起こしてしまい逆流性食道炎が発症します。
症状
- 胸やけ
- 食べ物が逆流する感じ
- つまり感
- げっぷ
- 食後の咳、痰がらみ などが起こります
原因
・胃と食道のつなぎ目の緩み(食道裂孔ヘルニア)
胃から食道への逆流を防いでいる下部食道括約筋の締め付け機能の低下。もともとの体質や加齢などで生じてきます。
つなぎ目が緩いと隙間から胃酸の逆流が起こりやすくなります
・食道の内圧低下
アルコールの摂取・喫煙などにより食道運動機能が低下し、食道の内圧が下がります。また、食道の蠕動運動を調整する機能の異常でも起こることもあります。
・胃の内圧上昇
食べ過ぎ、肥満、便秘、前かがみの姿勢、ベルトや下着による腹部の締めすぎなどにより胃の内圧が上昇し、胃酸の逆流の原因となります。
また、胃の内部にガンが発生して通過障害を起こすことも内圧の上昇につながり二次的に逆流を起こします。
・胃酸の分泌過多
ストレスや高たんぱく、高脂肪、香辛料、高カフェイン(コーヒーなど)の過剰摂取は胃酸の分泌の増加につながります。
・胃や食道の動きの低下
ストレスや睡眠不足などの生活習慣や抗うつ剤や抗不安薬などによって、胃や食道の動きや胃酸の分泌をコントロールする自律神経が影響をうけ、
胃の動きが低下や胃酸の分泌過多が生じ逆流性食道炎が発症します。
・唾液の分泌低下・アルカリ濃度の低下
唾液はアルカリ性なので食道に流れ胃酸を中和する作用がありますが、喫煙により唾液中のアルカリ濃度が低下するため、その中和能力が落ちます。
・粘膜の知覚過敏
食道の粘膜が過敏になってしまうことで、わずかな胃酸の逆流を症状として感じてしまうこともあります。
なぜ逆流性食道炎は治らないのか?ぶり返すのか?
①生活習慣やストレスの改善が難しい
胸やけの原因となる逆流性食道炎の要因には、胃酸の分泌過多や胃や食道の動きの低下が関わってきますが、これらはストレスや睡眠不足など生活習慣によってもたらされることが多いです。
胃酸の分泌や胃や食道の動きは前述のように自律神経がコントロールしているのですが、ストレスや生活習慣(食生活・アルコール・タバコ・睡眠など)の乱れがあるとコントロール機能が上手く働かず、胃酸過多になったり、胃や腸の動きが低下し、逆流性食道炎を起こし、胸やけが発生します。
ですので、ストレス因子が持続したり生活習慣を改善しないと、一旦薬でよくなったあともぶり返すことが多いのです。
そのため習慣の改善を行うことが大切になりますが、急激な習慣の改善が難しかったり、ストレス環境が続く場合には、薬を持続的に使用したり、胃酸の分泌を正常に保つようなサプリを使用することもあります。
②薬をやめるとリバウンド反応を起こす
胃酸を抑える薬を服用していると、薬をやめた際に一時的にリバウンド反応を起こし、胃酸が分泌しやすくなるため逆流性食道炎の再発を起こすことが少なからずあります。
そのため、薬がやめれないという状態に陥ってしまいます。
対応としては
・薬を徐々に減らしていく
・効果の弱いものに切り替えていく
・胃酸の分泌を正常化するサプリ“i-katsu”を服用することでリバウンドを出にくくする
などがあります。
このように生活習慣の改善やサプリの服用を行い胸焼けしにくい体質をつくることで、「脱・胸焼け」を目指します。
▶関連ページ:逆流性食道炎に対してのi-katsuでの治療
③逆流性食道炎を起こしやすい体質の治療が簡単にはできない
逆流性食道炎の原因には、「肥満」や「食道裂孔ヘルニア」といった体質が関わっていますが、これらの体質的な問題は簡単には改善できません。
肥満になると腹圧があがり胃酸の逆流を起こしやすくなりますし、食道裂孔ヘルニア(胃と食道のつなぎ目の緩み)があると下部食道括約筋の締め付け機能が低下することで胃酸の逆流が起こります。
肥満は一朝一夕では改善しませんし、食道裂孔ヘルニアの治療は特別な内視鏡治療や手術を行う必要があります。
ですので、このような逆流が起こりやすい体質の方は、より生活習慣に注意し、薬やサプリによる治療を適宜行います。
※食道裂孔ヘルニアの方で薬治療や生活習慣の是正でも逆流性食道炎が改善しない場合は、食道裂孔ヘルニア自体に対しての考慮する必要があります。
そのような場合は入院を要する治療となるため、対応できる高次医療機関へご紹介いたします。
④薬が合っていない
逆流性食道炎の原因の一つに粘膜の知覚過敏があります。
実際に内視鏡をやってみても炎症が見当たらないようなごく軽度の胃酸の逆流でも胸やけを感じてしまう状態です。
そのような方には、胃酸を抑えるだけでなく粘膜を保護するような薬や知覚過敏を抑える漢方などを併用しないとなかなか症状が改善しません。
また、逆流による炎症の程度が強い場合には胃酸を抑える薬をしっかりと使わないと症状は改善しません。
このように逆流性食道炎の原因や状態に合わせた適切な薬を選択する必要があり、国内外ガイドラインでも、病型・重症度に応じた薬剤選択と維持療法が推奨されています。
⑤診断が間違っている
そもそもの診断が間違っている場合には、いくら逆流性食道炎の治療しても治りません。
症状からは逆流性食道炎が疑われても、内視鏡検査(胃カメラ)を行ってみると「食道がん」や「アカラシア」「カンジダ」といった別の病気だったということも少なからず経験します。
症状が続く場合、薬を飲んでも治らない場合などには内視鏡をやって状態を把握する必要があります。
お電話でのご相談・ご予約は03-5940-3833
関連ページ:
治療方針|薬・サプリ・生活習慣の整え方
具体的な治療としては、
①症状を抑える薬やサプリ
②逆流性食道炎を起こしにくくする生活習慣つくり
を柱に行っていきます。
薬治療
- 胃酸の分泌過多を抑える制酸剤
- 胃の動きを改善し胃酸の流れをよくする薬
- 食道粘膜の知覚過敏を抑える漢方薬
症状の出現タイミングや逆流の原因には個人差があるので、患者さん一人一人の症状に合わせお薬の種類を変えたり、また薬同士の飲み合わせを行ったり、服薬時間の工夫を行っていきます。
また当院では「薬が効かない方」や「副作用が出て薬が飲めない方」「薬を飲むのに抵抗がある方」に対して、オリジナルのサプリ『i-katsu』を使用した治療も行っております。
関連ページ:
- なぜi-katsuは逆流性食道炎に効くのか?|i-katsuの詳細はこちら
生活習慣つくり
1.食事内容の見直し
・アルコール:食道運動機能が低下し、食道の内圧が下がります。
・高たんぱく、高脂肪、香辛料、高カフェイン(コーヒー・お茶):胃酸の分泌過多につながります。
2.喫煙を控える
喫煙は食道運動の低下、腹圧の上昇を招きます。また喫煙により唾液中のアルカリ濃度が低下するため、唾液が食道に流れた時に胃酸に対する中和能力が落ちます。
3.食べ過ぎない(腹八分目)
食べ過ぎて満腹になりすぎると、胃の内圧が上がってしまい胃酸や胃内容の逆流が起こりやすくなります。
4.食後すぐに横にならない・寝る前には食べない
食後と夜寝ている間は胃酸がよく出ます。
加えて横になる姿勢だと、食道の位置が低くなり重力もかかりにくくなるため、胃酸が逆流しやすくなります。
就寝時の頭側挙上も有効です。(ブロックやリクライナーを活用)
5.ベルトなどでお腹を絞めすぎない、適正体重を保つ
腹圧が上がり、胃酸の逆流の原因になります。
これらの生活習慣の見直しはガイドラインや系統的レビューでも推奨されます。
※前述のように、裂孔ヘルニアが原因となっている方で治療を行っても改善しない場合は、裂孔ヘルニアを閉じるような内視鏡治療や手術を考慮する必要があり、そのような場合は、入院を要する治療となるため対応できる高次医療機関へご紹介いたします。
お電話でのご相談・ご予約は03-5940-3833
実際の治療例
①30代 男性 薬をやめると胸やけをぶり返す
【症状】
以前から胸やけを繰り返しており、他院にて逆流性食道炎と診断され薬を内服していましたが、薬やめるとぶり返すとのことのことで当院を受診されました
【診察】
前医で施行された内視鏡(胃カメラ)検査の結果と症状から、当院でも逆流性食道炎と診断しました。
【治療】
前医ではPPIと呼ばれる制酸剤にて治療を受けて、飲んでいる間は改善するとのことでした。
PPIは胃酸を抑える薬ではありますが、内服をやめると抑えられた分の胃酸がそれまで以上に出てしまうという「リバウンド現象」を起こすことがあり、なかなか中止出来ずに飲み続ける、あるいは飲んだりやめたりを繰り返すことがあります。
当院オリジナルサプリのi-katsuはこの制酸剤のリバウンド作用を抑える作用も報告されており、ご本人が「薬を飲み続けるのは抵抗があり、なるべく薬は飲みたくない」との希望があり、i-katsuを併用し様子を見ることとしました。
1.生活習慣指導
症状があるときは揚げ物などの油物や高たんぱくの食事を控えていただくようにしました。
※高たんぱく、高脂肪、香辛料、高カフェイン(コーヒーなど)の過剰摂取は胃酸の分泌の増加につながり、逆流性食道炎を増悪させます。
2.サプリ(i-katsu)
制酸剤のリバウンドの抑制作用があり、薬の中止・再燃の防止作用が期待でき、またi-katsuはサプリ(食品)ですので、通常は副作用が出ることがなく、長期間安全に飲んでいただくことができます。
【経過】
PPIとi-katsuサプリを併用して治療を開始。
1週間ほどで胸やけは改善。PPIは中止し、i-katsuのみとしました。
普段はPPIを中止すると1-2週間で再発していたとのことでしたが、今回は再発もなく安定しており、i-katsuを続けながら快適に生活を送られています。
このように逆流性食道炎をぶり返しやすい方にi-katsuは有効なことがあり、長期服用による副作用などもほとんどないため、当院では多くの逆流性食道炎の治療に用いています。
②50代 男性 逆流性食道炎を繰り返す
【症状】
以前から逆流性食道炎を指摘されており、胸やけや胸の痛みなどの症状が出る度に薬を使って抑えていましたが、
今回も数日前から症状が出現したことに加え、あまりにも繰り返すため当院を受診されました。
【診察・検査】
逆流性食道炎の程度を評価し、治療方針を決定するため胃カメラを行いました。
胃カメラでは中等度の逆流性食道炎と診断し、まずは炎症を抑えるため投薬治療を行うこととしました。
胃と食道のつなぎ目部分に4か所の炎症を認め(矢印部分)、中等度の逆流性食道炎と診断しました。
【治療】
逆流性食道炎の治療は
- 胃酸の分泌過多を抑える制酸薬
- 胃の動きを改善し胃酸の流れをよくする機能改善薬
- 逆流性食道炎を引き起こす生活習慣の改善
を軸に行います。
今回は炎症が強いためPPIという制酸剤のと機能改善薬を合わせて処方することとしました。
症状は薬を服用した翌日から軽減し始め、4日目からはほとんど感じなくなったとのことでした。
炎症自体も2週間ほどの服用で一旦は消失しますが、そもそも逆流性食道炎が起こる原因には生活習慣が大きく関わっており、
その点の改善をしないとまたぶり返してしまうため、今回は以下の生活習慣の改善も行いました。
- 飲酒は2日毎に休肝日を作ること
- 油物や高カロリー食は2食連続して食べないこと
【経過】
薬を止めると以前は1か月ほどで胸やけ・胸痛が出ていたとのことでしたが、今回は強い症状は出ませんでした。
ただ、飲酒翌朝には薬を飲むほどではないが軽い胸やけを感じたりすることもあるとのことで、胃酸分泌過多を適正化するサプリi-katsuを使ってみることにしました。
胃のサプリi-katsuは乳酸菌と生薬で作られており、薬と違い副作用が出ることがなく長期の服用に関しても安全性が高く、症状がぶり返しやすい方・薬を飲むのに抵抗がある方・薬を飲むほどではないが症状がある方などの治療に使用しています。
その後は軽い症状の出現もなくなり、ご本人も改善した生活習慣の維持を続けておられることもあり、以前のようなぶり返しもなく安定した状態が続いています。
③30代 男性 食後に痰が絡んで取れない
【症状】
数か月前から食後に痰が絡むような感覚があり、症状が続くため耳鼻科を受診されました。
同院で喉のスコープ(喉頭ファイバー)検査やアレルギー検査を受けましたが異常なく、逆流性食道炎ではないかと言われ投薬治療となりました。
2週間ほど薬を続けたものの改善なく、近くの内科を受診され薬を変更されましたが、やはり改善なく当院を受診されました。
【診察】
痰がらみは主に食後に起こるとのこと、耳鼻科での異常がないことから、逆流性食道炎の可能性は高いと考えました。
胃カメラ(内視鏡検査)はまだ受けていないとのことで、胃カメラを行い状態を状態をしました。
【検査】
胃カメラでは胃と食道のつなぎ目部分に炎症を認め、逆流性食道炎の診断となりました。
実際の内視鏡画像です。胃と食道のつなぎ目に線状の炎症(黄色部分)を認め、GradeAの逆流性食道炎と診断しました。
【治療】
逆流性食道炎では胸やけやげっぷだけではなく、のどの違和感や食後の痰がらみなど様々な症状を引き起こします。。
前医で制酸剤が処方されていましたが、効果が弱いものであり症状の改善が得られなかったと考え、逆流性食道炎に適した制酸剤への切り替えを行い、
併せて胃の動きを改善する漢方の処方を行いました。
制酸剤はどれも同じわけではなく効果に差があるため、胃カメラで逆流性食道炎の状態を見極め、状態に合わせた適切な薬を選択することが重要です
治らない理由の「④薬が合ってない」に該当します。
また合わせて以下の生活習慣の改善に取り組んでもらいました。
- 休肝日を作ること、寝酒をしないこと
- 刺激物や香辛料の強い食事を2食連続してとらないこと
【経過】
投薬開始後、2日ほどで痰がらみの程度が低下してきて、2週間ほどで症状は消失し、一旦薬は終了としました。
ただ、逆流性食道炎はぶり返しやすく、本人からも予防をやっていきたいとの希望があり、
「引き続き生活習慣の注意点を守ることと」「当院オリジナルサプリのi-katsu」による予防を行い、その後も安定した状態を維持されています。
i-katsuにできること
✅胃酸の状態を適切に保つことで、逆流性食道炎の予防に効果
✅制酸剤中止後の“リバウンド現象”を抑制
✅乳酸菌+生薬のみで構成 →副作用が出ることはほぼなく 長期服用でも安心
i-katsuはこんな方におすすめです
-
胃薬をやめるとすぐに症状が戻ってしまう
-
薬に頼らず、体質から整えたい
-
軽い症状のうちに予防したい
-
長期的な再発防止をしたい
▶ i-katsuの詳しい効果は【こちら】
お電話でのご相談・ご予約は03-5940-3833
まとめ
-
逆流性食道炎が治りにくい理由は、生活習慣(遅い時間の飲食・飲酒・喫煙・肥満・前かがみ姿勢)や体質(食道裂孔ヘルニアなど)、そして薬のリバウンドが重なりやすいから。
-
再発を防ぐ柱は
-
酸分泌コントロール
-
運動機能・粘膜保護(機能改善薬・粘膜保護薬・漢方の適切な併用)
-
生活習慣の是正(減量、就寝3時間前以降の飲食回避、就寝時の頭側挙上、腹八分目、飲酒・喫煙の見直し)。
-
-
胃カメラで重症度の評価や他疾患(好酸球性食道炎・アカラシア・食道がん など)の除外も必要。
-
体質要因が強い・難治例では、専門医が外科・内視鏡的治療の適応を検討。
-
「薬を減らしたい」「中止後にぶり返す」方には、i-katsuを併用。
よくある質問FAQ
Q1. どのくらい治療を続ければ再発しにくくなりますか?
A. 炎症が強い場合はまず8週間程度しっかり治療し、その後は症状や重症度に応じて維持療法や段階的減量を検討します(ACG/日本ガイドライン)。
Q2. 就寝時にできる簡単な対策は?
A. 頭側を上げて寝ること(ベッド頭側の高挙上)は実証的に有効です。遅い時間の飲食は避け、左側臥位が楽な方もいます。
Q3. PPIをやめると胸やけが強くなるのはなぜ?
A. リバウンド酸分泌(RAHS)が起きうるため。医師の指示で漸減や切替を行いましょう。
Q4. 食道裂孔ヘルニアがあると言われました。手術は必要?
A. 多くは内科的治療でコントロール可能ですが、難治例や合併症がある場合に外科/内視鏡的治療を検討します。
Q5. 胸やけはあるのに内視鏡で「きれい」と言われました。
A. 非びらん性胃食道逆流症(NERD)や機能性胸やけ、知覚過敏などの可能性があります。必要に応じて高次医療機関でpHインピーダンス検査等で機能的評価を行い、治療を最適化します。
医師紹介
神谷雄介(かみや ゆうすけ)院長
📍経歴
国立佐賀大学医学部卒業後、消化器内科・内視鏡内科の道を歩み始め、
消化器・胃腸疾患の患者さんが数多く集まる戸畑共立病院・板橋中央総合病院・平塚胃腸病院にて研鑽を積む。
胃もたれや便通異常といった一般的な症状から、炎症性腸疾患や消化器がん治療まで幅広く診療を行いながら、
内視鏡専門医として年間3000件弱の内視鏡検査、および早期がんの高度な内視鏡治療まで数千件の内視鏡治療を施行。
2016年4月に巣鴨駅前胃腸内科クリニックを開業。
内視鏡検査だけでなく、胃痛・腹痛・胸やけや下痢などの胃腸症状専門外来や、がんの予防・早期発見に力を入れている。
- 日本内科学会認定医
- 日本消化器病学会専門医
- 日本消化器内視鏡学会専門医
🩺 診療にあたっての想い
胃や大腸の病気は、早期発見・早期治療がとても重要です。
「気になるけれど、どこに相談したらよいかわからない」「検査は怖いし、つらそうで不安」
そんな方にも安心して診察や検査を頂けるうような診療を心がけております。お気軽にご相談ください。
アクセス
所在地
〒170-0002
東京都豊島区巣鴨1丁目18-11 十一屋ビル4階
交通
巣鴨駅から徒歩2分、ローソン(1F)の4階巣鴨駅前胃腸内科クリニック
お電話での予約・お問い合わせ:03-5940-3833
文責:巣鴨駅前胃腸内科クリニック院長 神谷雄介
(消化器学会・内視鏡学会専門医)
お電話でのご相談・ご予約は03-5940-3833
参考文献
- Katz PO, et al. ACG Clinical Guideline: GERD (2022). Am J Gastroenterol. ガイドライン本文と推奨(生活指導・薬物・外科/内視鏡治療)。PMCgiboardreview.com
- Iwakiri K, et al. Evidence-based clinical practice guidelines for GERD 2021(日本消化器病学会).(ボノプラザン/PPI選択や維持療法の考え方)スプリンガーリンクPubMed
- Reimer C, et al. PPI中止後の酸関連症状(RAHS):健常者無作為化試験。Gastroenterology 2009. Gastro Journal
- Kaltenbach T, et al. 生活指導の効果(減量・頭側挙上):系統的レビュー。Arch Intern Med 2006. JAMA Network
- Fein M, et al. LES不全と裂孔ヘルニアの病態。Ann Surg 1999
関連ページ
・食道がん