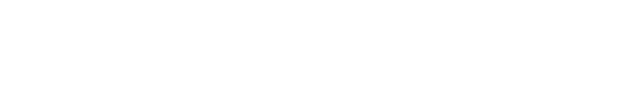患者さんからの質問【潰瘍性大腸炎の分子標的薬について教えてください】
潰瘍性大腸炎で通院中の方やセカンドオピニオンに受診された方から「分子標的薬」について度々ご質問を受けます。
近年潰瘍性大腸炎の新規治療として注目されている「分子標的薬」について解説させていただきます。
潰瘍性大腸炎とは?
免疫細胞の異常により大腸の粘膜に慢性的な炎症を起こす疾患です。
免疫細胞の異常がなぜ起こるのかという原因はわかっておらず、根本的に治す治療が未だにありません。
そのため生涯を通して病気をコントロールしていく必要があるため、国が定める「指定難病」にもなっています。
「分子標的薬」とは?
潰瘍性大腸炎の根本的な原因は不明なものの、粘膜に炎症を起こす免疫細胞や分子は特定されつつあり、炎症の原因となる分子に直接作用することで炎症を抑えこむ薬となります。
従来の治療で改善のない方・コントロールが不十分で安定しない方などに使用されます。
現在は6種類ほどの分子標的薬があり、いずれも粘膜に炎症を起こしている過剰な免疫を強力に抑えることができ、効果も期待できるのですが、副作用として感染に弱くなるといったデメリットもあります。
そのため体内に結核やB型肝炎などがある場合は再燃の可能性があり、治療導入前にそのような感染がないかをきちんと調べた上で行います。
それぞれの薬についてみていきましょう。
①TNFα阻害薬
「TNFα」という炎症反応に関与する生体内物質の働きを抑える製剤です。
「TNFα」はもともと人の身体に存在するものですが、炎症性腸疾患では異常に増加しており炎症の場で中心的に働いていると考えられています。
即効性が高く(効果発現まで数日〜数週間)、比較的炎症が強い方にも使用できるのが特徴です。
点滴製剤(レミケード)と皮下注射(ヒュミラ・シンポニー)の3種類があり、症状や希望の投与法に合わせて使用します。
②インテグリン阻害薬
インテグリンは白血球(特にリンパ球)が血管から腸管の組織に移動する際に使う“接着分子”の一種です。潰瘍性大腸炎では、この仕組みにより腸の粘膜にリンパ球が集まり、炎症を引き起こします。
インテグリン阻害薬は、この接着の働きを阻害することで、腸へのリンパ球の過剰な移動を防ぎ、腸管に限定した抗炎症効果を発揮します。
エンタイビオという点滴製剤とカログラという内服製剤があります。
腸管の免疫を選択的に抑えることで全身性の感染症のリスクは他の製剤に比べて低いという特徴がある反面、効果発現までやや時間がかかる(4~6週間)というデメリットもあります。
③JAK阻害薬
炎症を引き起こすサイトカインという物質の伝達酵素であるJAKをブロックする薬になります。
この働きをブロックすることで、複数の炎症経路を一度に抑制し、腸管の炎症を鎮めます。
潰瘍性大腸炎に使用できるJAK阻害薬はゼルヤンツ・ジセレカ・リンヴォックの3種類があり、いずれも内服薬で、即効性もあり数日で効果が見られるという特徴があります。
ただ、帯状疱疹などの感染リスクがみられることと、血栓症のリスクが指摘されており60歳以上・喫煙歴・心血管リスク因子のある方には注意して使用します。
④ヒト型抗ヒトIL-12/23p40モノクローナル抗体製剤
潰瘍性大腸炎の炎症を起こすサイトカインのひとつであるIL(インターロイキン)-12, IL-23という物質の作用を抑える薬剤です。
ステラーラとい薬剤で、2020年4月より潰瘍性大腸炎でも使用可能となりました。
初回は点滴で注射し、2回目は8週後に皮下注射、以降12週毎に皮下注射を維持治療として行います。効果が弱い場合は8週毎の皮下注射を行います。
副作用も比較的少なく、投与期間も長い(8-12週)という特徴がありますが、効果の発現までにはやや時間がかかります(2-6週程度)。
⑤ヒト化抗ヒトIL-23/p19モノクローナル抗体製剤
こちらも炎症を起こすもとのひとつであるIL(インターロイキン)-23という物質の作用を抑える薬剤です。
オンボーとスキリージという薬になります。
上述のステラーラがIL23と12の作用を抑えるのに対して、こちらの製剤はIL-23をより選択的に抑えます。
IL-23が炎症の強い要因となっている場合はこちらの製剤がより有効になってきますし、IL23と12のどちらもが要因として強い場合は④ステラーラの方が有効です。
ただ、実際は使用してみるまではどちらが有効かはわからないため、④と⑤のどの製剤を使用するかは投与方法などの違いで患者さんと相談して決めていきます。
・オンボー:導入療法4週間隔で3回点滴→維持療法:4週毎皮下注射(自宅でも可能)
・スキリージ:導入療法4週間隔で3回点滴→維持療法:8週毎皮下注射(クリニックで投与)
・ステラーラ:導入療法1回点滴→維持療法:8週後より12週または8週毎皮下注(クリニックで投与)
⑥S1P受容体調節剤
炎症を引き起こすリンパ球が腸の粘膜に移動するのを抑えることで潰瘍性大腸炎をコントロールする薬剤です。
ゼポジアとベルスピティという薬になります
本来、リンパ球(白血球の一種)は血管から組織に移動して免疫反応を引き起こしますが、潰瘍性大腸炎ではこの反応が過剰になり、腸管に炎症が生じます。
S1P受容体調節剤は、このリンパ球の移動をコントロールすることで、腸の過剰な免疫反応を抑える仕組みです。
従来の分子標的薬と作用機序が異なるため、①-⑤の薬でも効果不十分の方にも効果が期待できること、また内服での投与可能なことが特徴ですが、心機能に影響することがあるため心疾患の既往のある方には慎重投与となります。
実際どの薬がいいの??
どの薬を選択するかは
薬の特性+患者さんの状態や希望(「炎症の程度」や、「投薬方法の希望(内服o注射or点滴)」や「通院間隔」)
を加味しながらと相談して決めていきます。
例)
- 炎症が強く即効性が必要な場合は①や③
- 注射が苦手な方は内服の③や⑥
- 通院回数を減らしたい場合は④
- 過去に結核や帯状疱疹の既往があり感染リスクが気になる方は② など
| 目的 | 適する薬 | 特徴 |
|---|---|---|
| 内服で治療したい | ③か⑥ | 外来・在宅で完結可能 |
| 通院間隔を短くしたい | ④や⑤ | 注射・点滴での投与だが、間隔が長い |
| 感染リスクが少ない | ② | 感染リスクが低めだが、効果が出るまで時間がかかる。 |
| 症状が強い | ①か③ | 即効性が強い |
潰瘍性大腸炎の治療でお悩みの方、症状の改善がない方はお力になれますので当院にご相談ください。
◆まとめ◆
| 分類 | 主な薬剤名 | 作用機序 | 投与方法 | 投与間隔 | 特徴・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| TNF-α阻害薬 | レミケード ヒュミラ シンポニー |
TNF-αという炎症性サイトカインを中和し炎症を抑える | 注射(点滴または皮下) | レミケード:8週ごと点滴 ヒュミラ:隔週皮下注 シンポニー:4週ごと皮下注 |
長く使用され実績が豊富。抗体産生や感染症リスクあり。効果減弱時に注意。 |
| インテグリン阻害薬(腸管選択型) | エンタイビオ | 腸管へのリンパ球の移動を選択的に阻害 | 点滴 | 導入:0,2,6週→維持:8週ごと | 腸管特異的なため全身への副作用が少ない。感染症リスクが比較的低い。 |
| IL-12/23阻害薬 | ステラーラ | IL-12とIL-23の両方を抑制 | 点滴+皮下注射 | 初回点滴→8週後皮下注→以降12週ごと(または8週) | 通院回数が少なくて済む。効果の安定性が高いが、即効性はやや劣る。 |
| IL-23阻害薬 | オンボー スキリージ |
IL-23のみを選択的に抑制 | 点滴+皮下注射 | 導入:4週ごと3回点滴 維持:オンボー:4週毎皮下注(自宅可) スキリージ:8週毎皮下注(医療機関) |
IL-23が主因の症例に特に有効。ステラーラより選択的な作用。 |
| JAK阻害薬 |
ゼルヤンツ リンヴォック ジセレカ |
細胞内のJAK経路を阻害しサイトカインの作用を遮断 | 内服(経口) | 導入:1日2回 維持:1日1回 |
即効性があり、効果も強力。全身性免疫抑制作用あり、感染症・帯状疱疹リスクに注意。 |
| S1P受容体調節剤 | ゼポジア | リンパ球の腸管移動を抑制 | 内服(経口) | 毎日1回(導入期は漸増) | 注射不要。効果は緩やか。徐脈・肝障害・感染に注意。心疾患には慎重投与。 |
お電話でのご相談・ご予約は03-5940-3833
文責:巣鴨駅前胃腸内科クリニック院長 神谷雄介
(消化器学会・内視鏡学会専門医)